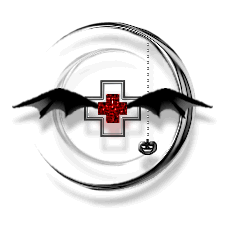
8. ニルヴァーナ
母親を呼んだのだと思った。
だが、吐き出した血を喉に詰まらせたせいで、ちゃんとした言葉にはなっていない。
事切れたばかりの遺骸を見下ろし、ナルトは不思議な感覚に首をかしげる。
忍者という仕事柄、何度も人の死に立ち会った。
今際の際に呟かれる声は、苦痛を伝えるものよりも、大事な人の名前だ。
ナルトの場合、顔も知らない母親を呼ぶことはあり得ない。
それなら、命の火が消える瞬間、思い出すのは誰のことだろう。
頬についた血の雫を拭って振り向いたナルトは、近づく仲間の気配に口元を緩める。「最後の一人、片づけたよ」
いつもの笑みを浮かべてナルトは状況を報告する。
里の極秘資料を持ち出して抜け忍となった元同胞。
もし、彼らが逃げ切れば、他国にスパイとして潜入している仲間達が危機にさらされていたはずだ。
裏切り者を始末するのに、躊躇いがあるはずがない。
「母親が病気で、治療のためのお金が欲しくて敵の間者と通じたみたい。病院に彼の全財産が送られてきたって」
「ふーん・・・・」
奪い返した資料を確認している途中、サクラからのいらぬ情報のおかげで、胸が悪くなる。
それなれば、殺さずに彼を逃がせば良かったのだろうか。
遺体を処理するための班が来るまでの間、ナルトとサクラの二人はその場所での待機を命じられていた。
繰り返される葬儀、人が死ぬたびに涙を流していたら、体が干上がってしまう。
それなのに、サクラは変わらず涙を流し続けるのだ。暗い顔で座り込んでいたサクラは、ふと、ナルトの頬を汚す染みに気づく。
「怪我、したの?」
「・・・平気」
ポーチから出した綺麗なタオルでサクラはナルトの顔を拭いた。
「無理して笑わないでね。そばにいるから」貼り付けた笑顔はすぐに気づかれる。
昔は、馬鹿をやって笑っていれば、みんなも自分を好きでいてくれると思った。
サクラがいれば、その必要はない。
どのみち、偽りの笑顔は見破られてしまうのだから。
「サクラちゃんの名前、呼んでもいいかなぁ」
世界が終わる、そのときに。